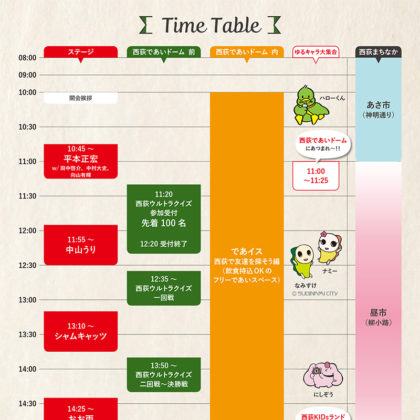「商い」の風景のある街
小さい頃の夢は「パン屋さん」だった。
私は能登半島の付け根のほうにあるちいさな街で生まれ育った。
その街は、進学・就職を経てたどり着いたこの街・西荻窪のように焼きたてのパンを買えるお店がたくさんあるわけではなく(魚屋さんならたくさんあったけれども)、美しい海とその恵みをささやかな観光資源とする自営業者の多い街だった。
いちばんの仲良しのA子ちゃんのおうちは和菓子屋さん、B子ちゃんと、あとCくんのおうちも魚屋さん(そう、そのくらい魚屋さんは多いのだ)、Dくんのおうちは料亭だからお弁当が豪華で、それが恥ずかしくてDくんはいつもお弁当の蓋を少しだけ開けて、その隙間からこっそりおかずを食べているということを私は知っている。
私の両親こそ先生だったものの、同じ市内にある両親の実家もやはり自営業で、特に小学校の近くにあった祖母の家に私は入り浸っていた。
土曜の昼、半ドンの授業を終えると決まって祖母の家に行く。祖母が「お店から好きなもん取って来られ」と言ってくれるのを待って、私はお目当てのメロンパンを手に入れるのだった。とびきりあまいメロンパン。
そう、ほんの子どもの私にとって「パン屋さん」とは祖母の家のことだった。タバコとヤ○ザキパンを中心に、お菓子や飲み物を商うその業態は、今でいうコンビニのようなものだろうか。
祖母は毎日店を開け、近所の人が毎日パンやタバコを買い求め、噂話をし、通りすぎていく。そんな日常は祖母が亡くなるまで続いた。
私が高校3年生の春に祖母はずいぶん急いだ様子で旅立った。
あまりに急いだものだから残された家族は憔悴した。私も真っ暗になった店先をひとりぼんやりと見つめていた。
あのとき、商品や什器が運び出されもぬけの殻となったお店を、代わりの何かで埋めようというのが、その後の大人になってからの私の人生なのかもしれないと思うことがある。
そういう意味で「パン屋さんになりたい」という夢はまだ捨てられずにいる。
最初東京なんて大嫌いだと思っていたのだけれども、この西荻窪になんとなく住み着いてしまったのは、この街にはそういう愛着のある「商い」の風景がそこかしこにあるからだと思う。「商い」をするとそこに人が集まり、つながりが生まれる。その網目が細かい街は居心地がいい。
西荻ラバーズフェスは今年が最後の、区切りの年。
でも、街のお店のひとつひとつの「商い」はこれからも続いていく、ということを忘れてはいけないと思っている。

協賛担当の役割は、運営のための資金や物資を集めること。だけど、西荻ラバーズフェス実行委員のメンバーの一人として、あるいはもっとシンプルに一住人として、街のために何ができるだろう、何が残せるだろうと考えて、今回協賛頂く方に提供するもののひとつとして、「記事広告」という形を取らせていただいた。
西荻窪には、いろんな考えを持って、こだわりを持って「商い」をしている人がたくさんいる。それはあらためて「言葉」など使わなくても商品や店先からにじみ出るものかもしれない。でも、そこを人類の最大の発明の一つである「言葉」の力でよりたくさんの人に知ってほしいのである。
知ることでまた思いもかけないようなつながりが生まれるかもしれない。ほんのちいさなものかもしれないけれど、変化を、化学反応を生み出せるかもしれない。
そんな淡い期待を持ちながら来週から、ひとつの楽しい読み物として、協賛企業さんにたっぷり膝を詰めて聞いた話を公開するので、どうか読んでほしい。
そしてその感想を身近な人と話してくれたりしたらとても嬉しい。
お店の方に声をかけてくれたりしたらもっと嬉しい。
これがきっかけでそこを利用してくれたりしようものならきっと泣くと思う。
少なくとも「楽しい読み物」という期待は裏切らない。だってお話を聞いた皆さんがとても魅力的なのだから。
ではみなさん、西荻であいましょう。
あれ、この「西荻ラバーズフェス」という店先を舞台に、私は今「パン屋さん」をさせてもらっているのとおなじではないか。
協賛チーム 小林真梨子